
救急隊員は、混乱や緊迫した状況下で必要な応急処置を行うという重要な役割を担っています。
その前段階として、関係者や傷病者に対して意思の疎通や情報収集のためにコミュニケーションスキルは必要不可欠です。
意識してコミュニケーションを取るか取らないかで全く結果が違う場合もあり、無駄な時間を費やして必要な処置が遅れてしまう場合もあります。
一般的に円滑にコミュニケーションを取るためには、聞き取り、理解、フィードバック、関心、誠意、質問、適切なトーン、適切な言葉の選び方、時間の管理などになると思いますが、救急現場においてはどうでしょうか?
救急隊の場合の多くは混乱した状況でのコミュニケーションとなりますので、傷病者や関係者に多くを望めません。
また、他の隊とのコミュニケーションでは伝える力が必要ですが、救急現場では聞く力の方が重要になる場合が多くあります。
今回は救急隊として現場経験から得た日頃から意識して行うべき以下のコミュニケーションスキルを5つご紹介します。
- 相手の話を理解する
- クリアなコミュニケーション
- 相手の感情に敏感であること
- 協調性
- 救急現場の雰囲気に対応する
相手の話を理解する

疑問点があれば話の内容を繰り返したり自分の言葉で言い換えたり、関連する質問をしたりすることで相手が伝えようとする内容を正確に理解します。
例えば「朝から頭が痛くしゃべりにくい」だけでは時間経過が不明確です。普段時計を気にしていない高齢者に「何時ごろからですか?」と聞いても「〇〇時頃かな~」ってなってしまいます。
いつも起きる時間、観るテレビ、朝ごはんの時間など聞いてそれの前か後かでかなり時間の精度は上がります。
また痛みであれば、最も痛かった時を「10」として今の程度を聞くことも可能です。
クリアなコミュニケーション

救急現場ではコミュニケーションを円滑に行うためには安定した口調で、専門用語を避けて簡単な言葉を使用し簡潔に知りたい内容を伝える必要があります。
痛みの表現などは特に表現が難しくズキズキ、チクチク、ヒリヒリ、ガンガン、シクシクなど感覚的感情的な表現になりますが、これは会話でもそのまま使用します。
搬送連絡時も痛みの表現は本人の表現のままが一番クリアです。
相手の感情に敏感であること

救急現場では、傷病者や関係者は恐怖やストレス、不安から感情が非常に高ぶっている場合があります。
救急隊員は、その様な感情に支配されている傷病者などに敏感に対応し寛容な態度を持つことで、理解してもらっていると感じてもらえ確実に繋がることができます。
相槌をうつ、うなずきながら聞くなどして相手が話すのを強制しないで、相手のペースに合わせて話を聞いている姿勢が伝わると核心部分に到達しやすくなります。
協調性

これは直接的なものでは無いですが、短い時間で効率的なコミュニケーションを行い傷病者や関係者が救急要請した目的を達成するために他の隊員との協調性が非常に大切です。
そのためには非言語化コミュニケーションをフル活用しいわゆる「阿吽の呼吸」で聴取している話を横で聞きながら他の関係者に説明や搬送準備するなどの対応などが必要です。
救急現場の雰囲気に対応する
最後になりましたが、円滑なコミュニケーションを行うために救急隊員が救急現場で最初に必要なことは救急現場の雰囲気に対応することです。
これはコミュニケーションを始める前に重要で状況評価【Scene Size Up】 に含まれます。救急隊員全員で救急現場の空気を読み共有することで、その現場での役割を決定することができます。
例えば、性的な被害を受けた女性の傷病者は、当然女性の救急隊員に対してより話しやすくなる可能性があります。これは一般論としての例ですが、目的は安心感や信頼感を高めて効率的なコミュニケーションを行う事です。
なので、女性隊員でも必要なコミュニケーションスキルが無ければやめときましょう。

まとめ
救急隊は、急な状況下でのスムーズなコミュニケーションが必要で、論理的な思考力や即座に正確な判断を下すことを求められます。
これらの能力は、最終的には目的とする迅速かつ効率的な救急活動に繋がるので傷病者happy、救急隊happyなwinwinになりますよ~。


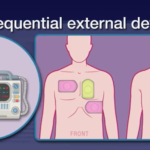
コメント